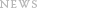

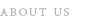



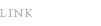






NEXT PROJECT > MOKK -solo-「f」からMOKKの4年間をめぐる【後編】

(左から)上村なおか、村本すみれ、寺杣彩
高橋:2012年1月に活動再開したソロシリーズ「Humming」から第2弾ソロ「f」へと何か繋がりは意識されましたか?
村本:「Humming」のチラシに書いたテキストに「一遍の詩が宇宙のように(広がる)」というのがあります。そこで、生まれ出てくるもののイメージとして唄声があり「Humming」を作りました。その次に自分がテーマにし得るものは何かと考えたとき、「エロス」だったんですよね。
高橋:エロス!
村本:でも、スタッフとブレストを繰り返していくうちに、「お前の言ってるエロスはエロスじゃない」と言われて(笑)。スタッフ全員、私以外は男性だったんですよ。5対1で、男性を相手に私がエロスを語るという状況。どちらかというと、「存続とか繁殖とか続いていくものだ」と言われましたね。そうやってテーマが固まっていきました。

40 放るワーク ワークショップのようす
高橋:出演者はどういう経緯で決めたのですか?
村本:3月〜5月にかけてオーディションワークショップを行いました。これは「f」だけでなく私自身今後作品を創っていくなかで、新しい魅力あるダンサーと出会いたかったからです。京都公演も決まっていたので、東京だけでなく京都・大阪でも開催しました。
高橋:大々的にワークショップをやったのは初めてだったんですね。
村本:そうですね。イメージとしてあったのは「透明感」から出現する「エロス」。引き出すからこそ現れるマグマようなものが欲しくて。だから、ワークショップでも参加者の皆さんと恋愛話をいっぱいしましたね。そこで、お会いしたときの透明感が半端なく強烈だったなおかさんにダメもとで声をかけさせていただきました。実はソロ作品を拝見していなかったのですが。
高橋:松尾さんは関西枠?
村本:そうですね。白神ももこさんなど演出家の方からの推薦も多くて。
高橋:きたまりさんや京極朋彦さんの作品に出ていますね。リハーサルはいつから?
村本:7月から本格的に始まりました。最初はずっと彩と、その後松尾、なおかさんと、リハを一人ひとりとやっていきました。
高橋:どのように創っていったのですか?
村本:「f」という作品は、私のなかで「エロス」から始まったけれど、「エロスじゃない」と言われましたし(笑)。それでも生理中にイライラしたり、外に出たくなくなったり、人を避けたり、それってホルモンが個体を繁殖へと向かわせるために、あえて肉体にプログラムされている働きだと思ったときに、「輪廻」を感じたんですよね。今回の出演者は年齢が違います。実は私は今のところ子供を産むつもりはなくて、彩はこれから生むであろう、と。そして、なおかさんはこれから産めなくなっていく可能性も高まるだろう、と。松尾は…分からない(笑)。それぞれ異なるなか、プログラムされている肉体の意識と、それぞれ自身が選択する道筋みたいなものをやっていきたいとは伝えましたね。
高橋:切実ですね。それを形にする際、身体を晒すことは避けられないと思いますが、観客に触れる場面もありました。ダンサーやスタッフと議論になったのでは?
村本:ブレストの段階でライブカメラの映像シーンとか、お客へのコンタクトをする、という案は既に出していました。しかし、スタッフから反対意見が多く「それは悪趣味だと思う」とまで言われたりもしました。でも、MOKKで劇場外の空間でこれだけ作品製作を続けてきたからかもしれないけど、出演者と観客という分け方ではない関係での触れ合いを大事にしています。
制作:見る人、見られる人、という狭間はあったかもしれないけれど。
村本:作品の中によりお客さんが入り込んでいく。くっきり別れているのが心地よいものではないと思っているから。そういう触れ合いが嫌であろう人がいるってことは理解しているけれど、今回のテーマを扱うにおいて外すことができないと考えています。
高橋:舞台であれば何をやってもいい、「表現」の自由が許されるべきという考えもありますが、実際どこまでやっていいのか難しいですよね。際どいところを狙っていたと思う。観客に触れたり晒し者になるようだったり。それと、観客との関係でいえば映像が壁面に映し出される場面で、松尾さんの目線やふとしたしぐさで壁の前にいたお客さんは退いたんです。目線や気配ひとつでそういうことが可能なんですね。偶然なのかもしれないけれど。とにもかくにも三者三様それぞれの性と生が立ち上がり浮き彫りになるのを間近で実際に感じました。

MOKK -solo-「f」東京公演 松尾恵美
高橋:村本さんの演出はどうでした?
上村:自作じゃないソロは初めてだったのですが、しっかりとした芯があり細やかな演出でした。いいと思ったこともすぐ言ってくれるし、反対に違うことは違うとずっと言い続ける。ダメ出しもね、多いんですけど(一同笑)、そのエネルギーはすごい。
村本:三人三様で振りは違います。違和感が無ければ問題ないですね。
高橋:難しい要求の連続だと思うのですが、お二人は不快に思ったり混乱したりしなかったですか?
上村:簡単にはできないとは思っていましたね。でも、必然性があるようにすみれさんが作品を創っていた。身体を晒すことについては、ダンサーだから(笑)やれちゃうけれど、触れることについては、この作品だからこそできたんだと思います。稽古中のダメ出しが厳しいんです(笑)。「そういう風には触れられない」とか具体的な指摘がとても多かったですね。そこがよかった。触れるということに納得がいけば、あとはそのときの流れですね。
高橋:寺杣さんは?今までの村本作品と違いました?
寺杣:はい。今まで「エロス」というのは求められてなかったはず(笑)。この話をいただいたときに「本当は私のイメージではないんだ」と言われました。誘うのも迷った、と。私の性格からしても抵抗感があってエロスは簡単には出せない。でも、ダンサーとして、そこに向き合うことは大事だと思った。それに本当の意味でのソロは初めて。話すだけでリハが終わることもあって、今までとは全く違いましたね。
どうやってもなおかさんや松尾にはなれないので、自分はどういう心持ちで向かっていくかっていうことを、常に他の人のリハーサルを観察しながら考えていましたし、一緒に動いてみたりもして。
上村:そうそう、「この手があったか!」って。一緒に動いちゃう。そうしたら、隣ですみれさんも動いていた(笑)。
高橋:Monochrome Circusを主宰している坂本公成さんがアゴタ・クリストフの戯曲とフランシス・ベーコンの絵画を題材に佐伯有香さんに振付けた「怪物」(2006年初演)というソロがあります。「歪んだ身体」がテーマのようですが、これは内外のさまざまな踊り手に踊り継がれ、かなりの上演回数を数えています。「f」は最初から3人の競演です。元々3人に踊らせるつもりでした?
村本:3人に意味はなかったけど、1つではなく、いくつかの道標を見せたかったんですよね。でも、3つが限界(笑)。産む、産みたくない、産めない、という選びとる3つの答えというのは、ちょっと考えていたのかもしれません。
寺杣:もし自分だけだったら、さらに悩んでいたと思う。悩みはしたけれど2人いたことに、とっても救われました。
上村:そうだね。まさに同志。いつも話し合ってるわけではないけれど、互いの稽古を見て、踊って、感じ合うというか、結構深いところで通じ合っているんではないかと思います。
高橋:3人だけで話したりした?
上村:小屋入りして楽屋に3人でいると言葉の数も少ないんだけど「よし、やろう。」みたいな、静かな心の会話があったと思う(笑)。いい空気が流れていましたね。踊るだけでなく公演そのものを惜しみなくやろう、と。
 上村なおか
上村なおか
高橋:実際に公演が始まって感じたことは?
村本:お客さんが作品の一部だと実感しましたね。もしくはお客さんだけで空間が作られてしまうくらい。たとえ美術や照明を作りこんでも、観客の立ち位置によっては、ある美術効果が出せない回もあったほど。1回1回の本番に対しての緊張感はとても高かったと思います。
上村:お客さんの行動は読めなかったなあ。あれだけ近づいて彩を囲むなんて。
寺杣:揺らされました(笑)。
上村:予想だにしなかったことがたくさん起きましたね。稽古である程度の想定はしていたけれど、本番では予想すらしなくなっちゃいました(笑)。
寺杣:東京では3回やらせてもらったけど、毎回空気が違うし、お客さんの居方も違う。作品の軸からはブレないようにと心がけつつも、私もその時の気持ちでやろうって決めていました。だけど、…ブレちゃったときもあったかな?
村本:あ、そうね(笑)。慣れることはないようですね。彩は昼と夜で回ごとに時間が違ったけど、やりづらかったりした?
寺杣:初日の夜はお客さんの数も多いし、お客さんが温かすぎるって思ったくらい。笑いも起きたりして、やりやすかった。でも、2日目の14時の回はシーンとしていて、お客さんの数も少なく散らばっているんですよ。集中の度合いは変わらないんですけれども反応があまり分からないからやりづらかったかな。3日目は時間の影響は特にないと思うけれど、昼と夜では一体感が違う気がします。
|
高橋:公演後の反応はいかがですか? 上村:「夜観てよかった」って言っていた人いたなあ。 村本:本当はもっと遅い時間に上演したかったんですよ。映画でいうところのレイトショーのような。 高橋:お客さんとの距離感でいうと、例えば男性が女性に対して投げかける、いわゆる“男の視線”なんかを感じました? 寺杣:性の対象としてはみられなかったと思う。でも、ものすごく抵抗されましたね……。私が触れているとき、そのときお客さんは出演者となってしまうわけで、一気に他の人から視線を集めるわけですよね。単純に恥ずかしいとか、見ないで欲しい、みたいなのは感じます。「来るな!」というオーラはあったかもしれません。 |
上村:最初のシーンに一番緊張感を感じるかも。そのあとはある種の関係性が見えてきて、お互い見る、見られるという共犯関係が自然と生まれ、お客さんは参加の覚悟ができあがる(笑)。
村本:そういえば、「黄金の雨」っていうギリシャ神話を感じたって言われましたね。その話を全然知らなかったので「へぇ〜」って応えたんですが。オイディプスの女性版みたいな話らしいです。(王が孫に殺されるという予言をされ、王は自身の娘を幽閉するが、娘は黄金の雨に身を変えたゼウスに誘惑され懐妊する。)
高橋:王女ダナエの話ですね。平山素子さんの代表作のひとつ「Life Casting-形取られる生命-」(2007年初演)のなかの「 Twin Rain 」は、その神話をモチーフにしています。生命の神秘や誕生を描き通じる点はあると思いますが、振付はもちろん作風・アプローチ・演出いずれも違う。「f」の場合、個の内面に深く分け入って生命の根源と不思議に迫っていて人間の根源的営みや存在の強さを感じました。
村本:なるほど。あと、よく私の作品を観てくれている方々からは「これまでの作品とは大分違うところにきた」という声を多くもらいましたね。
高橋:自分で手応えはあった?
村本:手応え?うーん。もしかしたらもうひとつのシーンを付け足さなければならないかも、と劇場入りの前、ダンサーに伝えていたんです。テーマをもっと掘り下げるような、根源的なものを足さなきゃならないかもしれないと。実際彩には稽古もつけていました。けれど、劇場入りし、美術、映像、照明が入り、観客がいると「あ、これは要らなかったな」と思いました。
上村:一見、美術や映像の要素が強いんだけれど「身体が見えた」って感想をもらいましたね。自分のなかでは「肉体が語る」いうよりも「世界を語る」って思っていました。
寺杣:「美術品、彫刻をみているようだった」と言われましたよ。
高橋:最初のシーンが陳列されているイメージだからね。
寺杣:「美しさを見た」っていう意見ももらった。3人全ての回を観た人には、特にこの人のこのシーンに一番共感したって言ってもらえたりしました。それぞれだなーというか(笑)。
村本:作品の話をすると、美しい世界を照明、映像、衣裳、そしてダンサー、どのセクションも作りこんでいるんだけど、例えば「美術がいい」とか「あの照明が」とか、どれかが突出した要素として勝ち得ているわけでなく、いい配分で戦っていて一つの世界感が出来上がったなあと思います。私も公演を迎えて「こういう作品だったか」と感じましたね。
高橋:身体と空間、美的な要素とモチーフが一体となっている。以前のLABOだと演出で持たせるところが大きかった印象はありました。今回は音響一つとってもお客さんを「f」という世界観のなかでどういう風に誘っていくのか、よく作り込んでいると感じましたね。無音や静けさも計算されている。観客を世界観に惹きこむ演出の微調整がうまい。3回観させて貰って実感しました。
高橋:京都公演を迎えます。地元在住の松尾さんが2回出られますね。
村本:松尾は二人に比べて稽古日数が少なかったのですが、10月には京都芸術センターでしっかり作り込む時間があるし楽しみです。ワークショップも開催します。あと朝11時の回があるので、この世界にどうやってお客を引き込むのかを考えていかなきゃと。
高橋:濃厚だから……。
村本:お腹いっぱいにはなってしまうでしょうね。そこはライトにする必要はないと思うんだけど。東京より一回り小さい空間ですが、3人の肉体をより深めていきたいですね。東京公演でも課題はありましたし(笑)、到着点は無さそう。「今日は今日の戦いを」と言って毎回送り出していたので、そこは京都でも変わらないです。
寺杣:東京公演では自分のなかで筋書きを立ててやってきたけれど、お客さんがいたら波立って遠くにふっとんでしまうようなところが多々あったんです。さらにしっかりとした軸を作っていかないと、さらわれちゃう危険があると思いました。
村本:よく松尾と彩に話していたんだけれど、自分が火花の散っている身体だとして、どんな色があってもいいんだけど自身が火花になってしまってはいけないんだ、っていうこと。身体自体が火花になってしまっては、その軸が無くなってしまうね、と。
高橋:軸がブレることへの恐れはある?
寺杣:やはり自分の作品ではないから。すみれさんの作品をソロで踊る責任は大きいなと思います。
上村:すみれさんは芯がしっかりあるのが良い。それをもっともっと掘り下げたい。作品なり身体の軸をしっかり強く持つことで、自由なところが深くできる。抽象的かもしれないけど船のイカリのように船底に沈められたら一番だと思います。だからもう一度京都で公演できることは嬉しいですね。
高橋:寺杣さんは村本さんと共同作業をずっとしてきた仲間だからこそ、できるってところはあるのでは?
寺杣:意識はしてないけど、あると思う。

(右より)寺杣彩、村本すみれ
高橋:いっぽう、初参加の上村さんが村本さんの思い描く世界に素直に入ったうえで独自の深い表現ができるのもさすがでしたね。京都公演で松尾さんに期待するところは?
村本:東京公演ではうまくいったところと、そうでなかったところはある。でも、その不安定さがおもしろいし美しかったりする。スタッフ内でも松尾のゲネを観て「うるっときた」って人がいたんですよね。それだけ振幅度が大きいからこそ共有感が強まるとすごい。だから私もそれを引き上げつつ、どれだけ芯の強いものを出せるか、可能性がたくさんあって楽しみ。
高橋:彼女はどこかふっと浮いているというか質感が違う……。
村本:3人のなかでは最も人間以外の生き物のよう。
高橋:そうそう。不思議な生き物を見た!って思った。
寺杣:ヘビみたい
上村:映画「スピーシーズ」に出てくる新しい生き物みたい。
高橋:珍獣が一人くらいいてもいいかも(笑)。
寺杣:でも普段話しているときと全然違う。
上村:身体の強さの切り口が鮮やかで面白いですね。
高橋:村本作品の世界観からすると、ちょっと異質の存在かも。
村本:三者三様とはいっても3人がいることによって作品が形成されている。たとえば、なおかさんの表現が私には思いもよらなかったとしても、それが作品世界の深さに繋がったりもする。
|
高橋:松尾さんは村本さんとの協同作業がまだ少ない面はあるのかもしれませんが、きちんと軸は共有しているんですよね。 村本:もっと深められると思いますし、その打ち合いを出せるかな。楽屋だと3人のなかでは一番人間ぽくって元気だよね。周りに目がしっかり向いていて、現場を元気にするエネルギーがあるんですよ。 高橋:「なでしこジャパン」じゃないけれども、結果的に3人の特性が活きて連帯感のあるキャスティングになったんですね。 一同:そっかー。 高橋:京都では松尾さんにホスト役になってもらってください(笑)。 |
すみれさんは、放し飼いの上手な作家さんだなと感じました。稽古中も、付かず離れず、広い視野で見守ってくれつつも、作品の枠から出ると指摘が矢の様に早く飛んできて、それが踊っていてとても刺激的であり、心地よかった現場でした。抽象的な言葉だったりするけれど、その中にきちんとしたイメージや理想像がしっかりある事が伝わるし、それを実現する為に、ダンサーと一緒に走ってくださる方で、心強かったです。
劇場入りしてからも、とにかく、必死でした(笑)。東京では、最終日に1回出演でしたが、自分の本番前になおかさんや彩さんのゲネプロや本番を目の当たりにできた事で、すごくイメージできる部分も多く、自然と本番に向けて腹をくくる準備ができていきましたね。スタッフの皆さんのパワーもすごく感じました。素晴らしかった。すみれさんや出演者のお二方にも、すごく支えて頂き、感謝しています。
観にきて頂いた方のために、精一杯踊ります。印象に残る、心に何かが刻まれるよう、しっかりとしたレールの中に込めるものを、自分の中でもっと深め、本番に臨みたいと思います!!